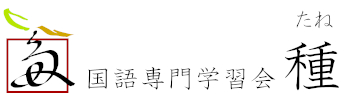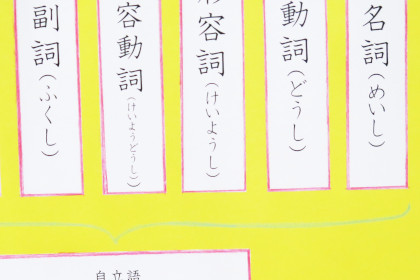敬語考①

先日、不覚にも敬語の使い方を間違えてしまいました。わたしの住まいに関することで、ある業者さんと電話で話していたときのことです。
「それに関しては妻が把握しておりますので、うかがっておきます。」と言ってしまったのです。
この話し方、どこが問題だったかというと、「うかがっておきます」のところです。敬語法としては少々ややこしい部類に入るケースだと思われますので、むしろ、何が問題なのか分からないと感じる人も少なくないかもしれません。
敬意の向かう対象
「うかがう」は「聞く」の謙譲語ですね。謙譲語というのは、自分や身内の行為にへりくだったニュアンスを伴う表現を用いることで、その行為の向かう相手を高めるというものです。「こちら」を下げることによって、結果的に「あちら」が目上になるというわけです。ここでは話者である私の行為を表すものとして使われていますので、その意味では正しいように見えます。しかし、この「うかがう」という動作が向かう対象が誰なのかを考えなければなりません。「行為の向かう相手」が必ずしも「話し相手」を意味するわけではないのです。
今回のケースがまさにそうで、「話し相手=業者」さん、「『うかがう』という行為の向かう相手=妻」でした。つまり、「うかがう」という謙譲語が高める相手は妻になってしまうのです。敬意を表するべき業者さんを差し置いて身内を高めるということになってしまうので、よろしくない敬語の用法だということになるわけです。
今回の場合には、「それに関しては妻が把握しておりますので、聞いておきます。」と言うべきでした。行為の向かう相手を上げることなく、ただ話し相手への敬意を表するには、丁寧語にするだけで良いのです。
と、まあ、国語を教えている身として、このように理屈をわかっているつもりですが、実際的な会話の場面では、その知識と口から漏れ出る言葉がかみ合わないということがしょっちゅうあります。今回のような敬語のケースのみならず、「ら」抜き言葉を使ってしまったり、助詞を変な風に使ってしまったり、しゃべった後に「あっ、しまった…」となってしまうことがしばしば。頭の中に言葉の体系が準備されていても、いざ発語する場面となると全然その通りに言葉を扱えない。これが世にいう口下手というやつなのでしょう。
敬語の論理性
ところで、以上述べた敬語の理屈を読まれて、やはり敬語というものは厄介だと思われた方も少なくないかもしれません。確かに、相手に敬意を、という思いから自分の行為に謙譲語を使っても、それがいつでも正しいことにはならないのですからね。関わる人が増えていくほど、気を付けて尊敬・謙譲・丁寧語を使い分けなければならないのです。これはとても難しいことです。
ただ、悪趣味に思われるかもしれませんが、私個人としては敬語にややこしさを感じつつも、やっぱりちょっと面白いなとも感じています。
何が面白いかと言えば、敬語がとても論理的で、ブレがないというところです。客か身内か、目上なのか否かといった、話者と対象(話し相手とは限らない)との客観的な関係性という観点のみによって完璧に用法が規定されています。それをきちんと押さえていれば正しい、外してしまえば誤用というふうに、正誤がはっきりしているのです。多義性、基準のあいまいさ、原理・原則の例外がかなり多い国語という分野にあって、この厳密さは目を引くものです。
なお、今回の電話の件で、私は相手の業者さんを尊敬する思いから敬語を使ったわけではありません。もちろん、その方を人として蔑ろにする気持ちを持っていたわけでもありませんが、相手への敬意よりも、社会的マナーという形式的な動機が圧倒的に強く働いて私に敬語を使わせていました。敬語は客観的な関係性だけによってあり方が決まるので、話者が主観的にどう思っているかは敬語のシステムにとってはあまり本質的なことではないのですね。
「敬意」という主観的な感情と大いに関係があるはずの言葉遣いでありながら、その感情の有無に依存せずに成り立っているのです。むしろ感情を入れ込まず、冷徹に話者と対象との客観的関係性を表示していくものなのだと言っても良いのかもしれません。敬語の厳密さは、この感情への依存性の無さに起因しているのかもしれません。
敬語は人のためならず
敬語を使うことと敬意を持つことは別系統の問題なのですから、たとえ敬語を使われても、それだけで相手が自分に敬意を持っているということにはならないのですね。たとえば「なんだ、あなたはそんなこともご存じないのですか」など、尊敬語と丁寧語をしっかり使った蔑みの表現だって往々にしてあるわけです。
また反対に、もしも敬語を使わないことで相手より偉く優位な立場になった気でいる人がいるとしたら、それはただの勘違いだということも言えるでしょう。敬語が話者と対象との客観的な関係性に規定されているに過ぎないのであって、敬語の方がその関係性を規定するということはあり得ないからです。敬語を使わないからといって、事実としての人間関係が転倒されることなどないわけです。
このことは、敬語の不使用は相手の顔に泥を塗ることにならないと言い換えることもできるでしょう。敬語を使うべき場面で使わないということは、その当人を社会的な人間関係への配慮を放棄した非常識者であるということにしこそすれ、相手の面目には何のダメージも与えられないのです。相手を貶められず、かえって自分の価値を下げるばかり。それならばやはり敬語は使わないより使う方が得策なのではないかなと思えてきます。敬語というものは、相手のためではなく自分のために使うものなのかもしれません。
(山分大史)