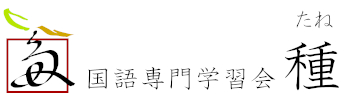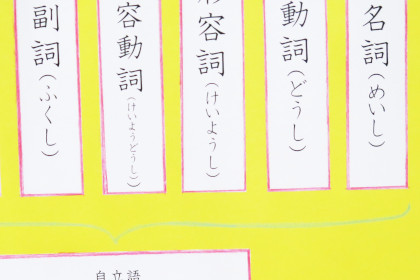コラム:具体的に書くために
3月に出版した『言葉の仕組みを学ぶレッスン』で、「具体と抽象」をテーマにして書いたところがある。その中で、よい文章を書くということは、すばらしい語彙や表現を使うということなどではなく、まずは「具体的に書く」ということであるということを書いた。
そして、この「具体的に書く」というのは、ある程度意識してやらなければできないことなのだということも書いた。具体的に語ろうとする意識を持たなければ、文章は自然と抽象的になっていってしまう。自分の文章の読者が頭のなかでありありと思いうかべられるように文章を書くためには、できるかぎり具体的に書くという意志の力が必要だ、という趣旨である。
『言葉の仕組みを学ぶレッスン』では、分かりやすさを優先して、それ以上はあまりくわしく立ち入らなかったのだけれど、実はこの点についてもう少し語ってみたいことがあるし、また本の出版後に改めて考えたこともある。今回はそれらについて書いていきたい。

抽象化をするために言葉がある
まず、文章が自然と抽象的になってしまうのは言葉というものの本質に起因することだ。言葉はそもそも抽象化をするための道具である。「りんご」という名詞は、大きさ、形、色、傷、熟し具合など、現実に存在するひとつひとつのりんご各々が持つさまざまな個性をそぎ落として、「りんご」という果実全般を指し示す。言い換えれば、「りんご」という名詞ひとつが指し示すのは、この地球上に現実に存在している特定のりんごのどれでもないということになる。「特定のりんごではないりんごを指す」なんて、すごく変な話だが、そんな変なことをする必要のある場面はこの世に山ほどあるし、そんな変なことをできてしまうのが言葉というものだ。
誰かが「りんごが食べたい。」とだけ言ったならば、その人は特定のりんごを欲しがってはいない。この世界のどこかのりんご園で育てられ、いまどこかの食卓の上に転がっているはずの、ひとつの特定のりんごを食べたいと言っているわけではないのだ。
りんごならば何でもよいから「りんごが食べたい。」と言う。こんなふうに、現実がまとう個性にしばられてはならなかったり、目の前に実在していないものを指し示す必要があったりする場面が私たちには何度も訪れる。そのときに必要なのが抽象化という作業だ。
言葉を扱うとは、この抽象化という作業をすることだ。学問をするのも、文学を創作するのも、この言葉のはたらきがあってこそ可能だ。言葉がなければ、抽象化という能力が実現できなければ、人間は高みにいけないのである。
具体化=言葉に不得手なことをさせること
話をもどすと、以上の通り、そもそも言葉の本質が抽象化にあるのだから、逆に言葉をつかって具体的なことを言い表そうとするのは骨の折れる作業になるわけである。もし、どんなりんごでも良いのではなくて、昨日スーパーで買った、青森県産の、甘みが強いりんごが食べたいのならば、「りんごが食べたい。」と言うだけではその欲求を表現できない。「昨日スーパーで買った、青森県産の、甘みが強いりんごが食べたい。」と言わなければならない。つまり、言葉を尽くして、どんなりんごを食べたいのかを特定させていかなければならないのだ。
言葉を扱うこと自体がすなわち抽象化なのだから、その逆の具体化をするということは言葉に不得手なことをさせるということだ。だから、言葉に負荷をかける必要がある。言葉に負荷をかけるのだから、その言葉を扱う自分自身も負荷を負うことになる。
そんな負荷を上手にクリアできる人が、言葉の扱いが上手い人、つまり文章を上手に書ける人なのだと私は考えている。だから、作文が上達するとは、具体的に書けるようになるということとほぼ同じだと考えてよいと思う。
具体的に書くために
実際、作文を子どもたちに教えていると、私の仕事の七割くらいは、子どもたちに具体化を適切にさせることだと感じる。本文を読んでくださっている方の多くが経験したことがあるのではないかと思うけれど、子どもたちが作文をしなければならなくなったときに真っ先に言う弱音が「書くことが無い」だ。多くの人が、指定されている字数に全然届かないで嘆くものである。原稿用紙3枚? そんなの絶対に無理に決まってる! 3行で終わっちゃうよ…。何書いたらいいの?
そんなふうに困っている子どもたちに対して、してあげられるサポートとして、まずひとつには作文のネタになる話題を一緒に考えてあげたり、あるいは子ども本人が思いつけるように対話をしてあげたりするというのが考えられるだろう。けれど、そんなふうに新しい話題を増やすことよりももっと大事なこととして、ひとつの話題をどれだけ具体的に表現できるかの道筋を示してあげることというのがあると思うのだ。
たとえば、読書感想文。「おもしろかった」くらいしか思いつかないというのであれば、その「おもしろかった」を具体化するのだ。いろいろ方向性は考えられるけれど、ひとつには、読み始めてから読み終えるまでの時間に目を向けて書くというのがよいかもしれない。普段読む本よりもずっと集中できて早く読み終えたとか、読むのが楽しみで休み時間になるのが待ち遠しくてならなかったとか、そういうことが伝われば、「おもしろかった」という感想に具体性が生まれる。字数のボリュームが確保できるだけではなく、感想に確かな説得力がつくのだ。(読書感想文で書くことが思いつかない場合の対策については、以前書いたこちらの記事も参考にしていただければ幸いです)
「時間と空間」を考える
いま、「時間に目を向けて書く」ということに触れたけれど、実は、ものごとを具体化する上でおさえておくべき大事なポイントのひとつが、「時間と空間」なのである。要は、「いつ」と「どこで」の情報。この二つを明確にしておくと、語りが具体的になる。
逆から言えば、時間と空間が伴われない状態が抽象的なのだ。単に「りんごが食べたい。」とだけ言ったときの「りんご」はこの世のどこかに実在する(あるいは実在した、実在するであろう)特定のりんごを指していないように、抽象的なものは特定の時点や特定の地点に位置を占めていない。抽象的なものは、時間と空間という属性を持たないのである。
だから、具体的であるということはその正反対で、その対象を取り巻く時間と空間が明確にあるわけだ。「昨日スーパーで買ってテーブルの上に置いておいたりんご」のように、時間的情報と空間的情報を特定できる。だから、それらにしっかりと目を向け、すくいとろうとすること、それがものごとを具体的に語るために必要な心構えのひとつだ。
具体的な動詞と抽象的な動詞
また、動詞のなかには、具体的に何をしたのか、何があったのかがある程度はっきりと表されるものとそうでないものがあるということにも留意しておきたい。たとえば、「歩く」という動詞を聞けば、どういう行動を具体的にとるのか、言うまでもなくはっきり思いうかべられるだろう。それに対して「学ぶ」はどうか。知識的なことがらを、本を読むなどして修得するのか、あるいは身体技術的なことがらを、実際に体を動かして習得するのか。あるいは、先生のもとで講義を受けるのか、それとも独学なのかというちがいもある。このように、様々な「学ぶ」のかたちが存在するのであり、この語ひとつでは、そのなかのどの行動が結局のところなされたのかが見えてこないのだ。
この例のように、動詞には、特定の行動や出来事を端的に表現するものと、様々な行動・出来事の集積となっているものがある。言わずもがな、前者は具体的で、後者は抽象的なのである。要は、後者は「肉体が見えない言葉」と考えてよいかもしれない。「歩く」であれば、脚という肉体の一部の運動がしっかりと見えるが、「学ぶ」はそうではない。
「学ぶ」以外には、たとえば「がんばる」「努力する」「つと(努・務)める」「目指す」「成功する」「配慮する」「導く」「支援する」「重んじる」といった動詞がこれにあてはまる。こういった動詞は、活動報告書や志望理由書、学習計画書などといった、高校や大学受験、あるいは就職活動にも関わる文書に使われることが多い。そのような類の文書でこうした「肉体が見えない言葉」を排するべきだというわけではないのだが、使用には気を付ける必要があると思うのだ。このタイプの言葉ばかりを使っていれば、ともすると、抽象的な文章、つまり受け取り手に実感を湧かせにくい空疎な内容の文章になってしまう恐れがある。
それを防ぐためには、「肉体が見える動詞」の入る文を織り交ぜたり、時間と空間についての情報がしっかり定位される語句や文を補ったりするのがよい。単に「中学時代は〇〇部のキャプテンとして部員たちの心をまとめることに努めました。」だけ語るのではだめだ。「努めた」の内容が見えないのである。どのようなときにどこでどのような行動をとったか、その結果部員たちがどのような行動をするようになったか、そういったことがらを添える。そうすることで、「努めた」に具体的な説得力が備わるのである。