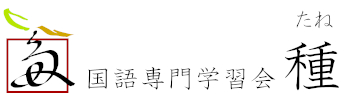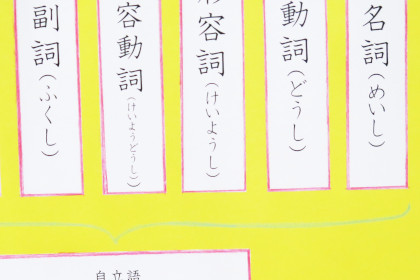「文学ワークショップ ~地の文をつくろう~」開催報告

芦屋川にお店を構える古書店、風文庫さんで「文学ワークショップ ~地の文をつくろう~」を開催させていただきました。
学習会のオリジナル教材としておなじみの「地の文をつくろう」を一般の方に楽しんでいただく場を開かせていただきました。機会をくださった風文庫さんは、お店の一部をワークショップスペースとして、普段からさまざまな催しを開かれています。店主さんに「地の文をつくろう」を紹介したところ、「とても面白い!」と気に入っていただき、今回のワークショップ開催の運びとなりました。
学習会をとびだし、他のお店をステージとしてお借りするというのは初めての試みであったため、反響がどのようであるか心配でしたが、告知開始から間もなく定員5名が埋まってしまうという嬉しい事態。やはり古書店である風文庫さんにいらっしゃるお客さんには、文学や言葉へのアンテナが鋭い方が多いのでしょう。そういう方々に魅力を感じていただけたのは非常に嬉しく思いました。
今回のお題
さて、会話文のみで描かれた場面から物語を想像し、そこに地の文を加えるというのが「地の文をつくろう」という教材の内容ですが、今回のワークショップで参加者の皆さんに取り組んでいただいたのは、こちらの会話文です。
「…ねえ、あそこ」
「ん、どうしたの?」
「うわっ、よりにもよってどうしてここに?」
「知らないよ。見られたらまずいよね。どうしよう」
「と、とりあえずあそこに入ろう」
「ふぅ、通りすぎて行った」
「気付かれないで良かった。どうなることかと思った」
2019年3月に行った種文学賞で出題したものに、若干のアレンジを加えたものを今回の題材にしました。人によりさまざまの物語が思い浮かぶ会話のやりとりになっていると思いますが、実際に今回のワークショップでも、この会話文をもとに参加者のみなさんそれぞれの個性のある作品が生まれました。
先生に叱られないように学生たちが身を隠す物語。とある式典に向かう二人が畏怖する人物から隠れようとする物語。誰にも見られずにたどり着けば願いが叶う場所に向かおうとする子どもたちの物語……。登場人物のイメージや世界観も個々それぞれの物語が生まれました。
言葉でしか表現できないことをする地の文
さて、今回のワークショップを通じて参加者のみなさんに特に感じていただきたいと意識していたことが二つあります。それは、「言葉でしか表現できないものがあること」、また「それを表現するのが地の文の大きな役割の一つである」ということです。
たとえば、夏目漱石の『三四郎』の中にこんな一節があります。
「風が女を包んだ。女は秋の中に立っている。」
主人公三四郎がヒロインの美禰子と初めて言葉を交わす機会が訪れた場面にある一節です。この「女は秋の中に立っている」という表現は、まさに言葉にしかできないことを言い表すものの好例だと思うのです。
「言葉でしか表現できない」というのは、絵や映像といった他の媒体では表現することができないということです。たとえば紅葉した庭に立つ女性を絵に描いたり、そのような庭のセットにモデルや女優を立たせてカメラで撮影したりすることによって、〈秋の風景の中に女性が立っている〉という画をつくることはできるでしょう。しかしながら、私たちはその画を見て〈女は秋の中に立っている〉という感覚を得ることはできるでしょうか。答えは否だと思います。〈女は秋の中に立っている〉という感覚は、「女は秋の中に立っている」という言葉で紡がれることによって初めて認識することができる感覚です。この言葉の助けを借りない限りは、絵や映像のみの力でこの感覚を表現するのは不可能ではないでしょうか。
こうした、〈言葉でしか表現しえないもの〉を表現することが文学であり、またそれができるということが文学の文学たる所以なのだと思います。そして、地の文は文学にとってそのための主な手段になるのです。
話が遠回りをしてしまいましたが、今回のワークショップでは、以上のような地の文の役割に参加者のみなさんが少しでも注目してもらえればという気持ちで臨みました。実際、参加者の書かれた作品の中には、この観点で印象に残った一節が確かにありました。その一つをご紹介しましょう。
「…ねえ、あそこ」
「ん、どうしたの?」
集君が指をささずに手の平でさした先にはあの着物姿の大御所が。
「うわっ、よりにもよってどうしてここに?」
この方は、二つ目と三つ目の会話文の間にこのような地の文を入れてくれました。注目したいのは「指をささずに手の平でさした先」という表現です。多くの人が見慣れており、何の新鮮さもないように思える動作かもしれません。そんな指し方を誰しもがしたことがあるでしょう。「それを言い表したからといって何なの?」と不思議に感じられるかもしれません。
しかしながら、これはまぎれもなく文学の粋を感じ取れる表現なのです。まず、この些細な身振りの表現は、ただ身振りを叙述するだけにとどまりません。「大御所」と呼ばれる人物に対する「集君」の敬意や畏怖の思いをきちんと匂わせています。しかも、ここで表現されているものは決して映像化され得ないのです。映像化されるのは、ただ手の平を向けている姿でしかなく、決して〈指をささずに手の平でさした〉姿ではないからです。まさに文学の仕事をきちんとやっている一節だと言えるのです。

他の参加者のみなさんの作品も、それぞれに文学の味わいや意義を感じられる表現が詰まっていました。そうした作品たちをみなさんで共有できたのは本当に楽しいひと時でした。今回のように多くの方と「地の文をつくろう」を分かち合える機会は、是非ともまたお作りしたいと思います。
「地の文をつくろう」は、こくごネットと共同開発・発信しているコトバクラフト教材として公開もしています。この記事をお読みになって、もし興味をお持ちいただけたら、ぜひチャレンジしてみてください。「これぞ文学」と言える仕事を果たす地の文を探究することを楽しんでいただければ嬉しいです。
(山分大史)